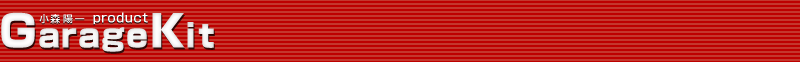
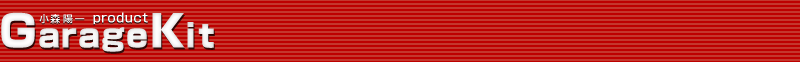
|
|
トップページ > ウルトラマンシリーズ > ザンボラー |
|||||||||||||
| アトラゴンGK 灼熱怪獣 ザンボラー
Chapter of ULTRAMAN 〜ZANBOLAR〜第32話 『果てしなき逆襲』より 灼熱怪獣 ザンボラー アトラゴンGK ウルトラ怪獣シリーズNO,004 |
||||||||||||||
 これまでに何度も書いてきた改造怪獣のこと。特撮の宿命ともいうべき制作費の高騰により、苦し紛れに編み出された手法だが、彼等はそれを逆手に取った。アイディアと造型でまったく新しい魅力を表現したのである。彼等とはいわずもがな、成田亨氏と高山良策氏のことだ。ガヴァドンBを改造することはおそらく前提だったのだろう。成田氏は改造怪獣の鉄則として、シルエットを大きく変えずに観ている者の目線を変えさせることをやった。つまり、目立った特徴、言うなれば強烈な個性を加味させるのだ。ジラースの襟巻、カボラの開閉するヒレ、ギャンゴの派手なお腹、バルタン星人のハサミと挙げていけば枚挙に暇がない。このザンボラーも背中にオレンジ色の発光器を備えることで、観る者にガヴァドンを忘れさせることに成功している。お腹や脚はそのままだというのに、だ。  ザンボラーの原型は宮崎逸志氏の手によるもの。思えば大阪のガレージキット店舗、GILGILさんに宮崎さんから連れて行ってもらった時、ショーケースの中にこのザンボラーが飾られていた。ご本人自ら嬉しそうに操作して、発光のギミックを見せてくれたことを今でもはっきりと覚えている。本当に子供のような笑顔だった。それにしてもよくぞまぁ細かいところまでこだわって造られている。身体に貼り巡らされた四角い鱗には折り目もあれば皺もある。大きさだって違う。これ一つとってもどれほど時間がかかったのだろうかと気が遠くなる。神は細部に宿るというが、宮崎さんの造ったものに触れていると、まさしくその通りだと頷ける。  彩色はまずクリアパーツから取りかかった。角と発光器をいかに電飾したように美しく輝かせられるかがテーマだ。クリアオレンジやクリアイエローをベースにしつつ、汚したり、また塗り込んだりした。凹凸部分や突端、真ん中、付け根がどうなっているかを写真を眺めたり、自分の想像力で補ったりして陰影をつけた。実際の溶岩の写真なども参考にすると、より面白い表現が可能になると思う。それが済んだらいつものようにフラットブラックから始めて、その上から土地色を被せた。ベース色はこれだけだ。ザンボラーの彩色によるポイントはズバリ青味だと思っていたので、フィールドブルーでアクセントを付けた。四つ足怪獣を作る上で気をつけなければならないのは組み立てだ。焦って両手両足、尻尾を接着してしまうと、どうしても塗りにくい部分が出て来てしまう。達人の方々は「見える部分には筆が届く」と言われるが、僕には到底無理な話なので、ギリギリまで接着をせずに彩色した。しかも、両手両足をくっ付け、パテ埋め、均し、彩色をしてから尻尾を付けるという念の入れようだった。細部までしっかりこだわって制作したい方にはこのやり方がお勧めだ。  これでまた一つ、約束が果たせた。天国にいる宮崎さんからは「遅いよ〜 小森さん」言われていそうだが(苦笑)         
|
||||||||||||||