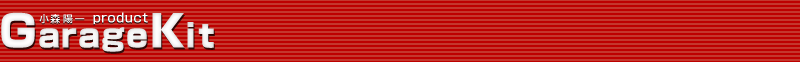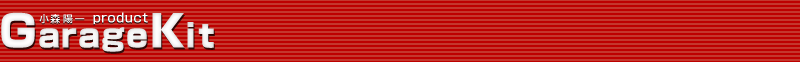牛を供養する鼻ぐり塚から鼻ぐりを盗んで腕輪にした若い男は、ヤプールに牛の呪いをかけて変身させられた。若き日の蟹江敬三さんがクセのあるバカチン野郎を熱演していた。まぁ、昔も今もこの手の類は後を絶たない。つい最近も万里の長城でお尻を出した日本人のユーチューバーが中国の警察に捕まった。そりゃ当然だろう。中華の怒りはヤプールより遥かに怖ろしいかもしれない。
牛を供養する鼻ぐり塚から鼻ぐりを盗んで腕輪にした若い男は、ヤプールに牛の呪いをかけて変身させられた。若き日の蟹江敬三さんがクセのあるバカチン野郎を熱演していた。まぁ、昔も今もこの手の類は後を絶たない。つい最近も万里の長城でお尻を出した日本人のユーチューバーが中国の警察に捕まった。そりゃ当然だろう。中華の怒りはヤプールより遥かに怖ろしいかもしれない。
そんなカウラの回、子供心に怖ろしかったという記憶がある。うちの奥さんも牛になった蟹江さんの姿を覚えているそうだ。他にも「怖かった」という方が何人もいらっしゃるので、やはり相当なインパクトがあったのだと思う。サブタイトルに怪談と付けられているから当然かもしれないが、昭和の子供番組は怖がらせる時は容赦なくきっちりとやる。だから記憶の底に貼りつく。本気で番組を作っていた証拠だろう。
そんなカウラを造ったのはやはりこの人、ゴートの杉本浩二氏だ。原型写真をひと目見た時から、圧倒的なディティールを感じた。デザインを担当した鈴木儀雄氏の特徴である『生物的な身体に硬質な装甲を纏わせる』という意匠がこのカウラにもなされている。柔らかい毛と硬い皮膚という、相反する性質を粘土で造り上げることは、泣きたくなるくらい大変だと思うのだが、杉本さんはその硬軟という難関をきっちりと仕上げている。それも全体のバランスを崩さずに、かつ、着ぐるみよりも見栄えよく。こんなことは怪獣(超獣)に対して愛のある人しか出来ない。だからこそ、それを台無しにしないようこちらも向き合わねばならない。
彩色はいつもとは違うアプローチで行った。黒をベースにするのではなく、最初から筆を使って体毛の茶色と硬い鎧の青色を塗り分けるのだ。茶色は土地色、青色はミディアムブルーである。きっちりと色分けをしていておいてから、陰影など細部に手を加えていった。その方が派手な超獣らしく、くっきり鮮やかに色分け出来ると思ったからであるのだが、段取りの多さも理由の一つだ。先に胴体と足や尻尾をくっ付けてしまうと、力士の化粧まわしのようなひらひらの内側が塗れなくなる。その化粧まわしも細かくパーツが分かれており、一つを仕上げて新たなパーツを取り付け、パテ埋めと削り(均し)を行わなければならない。その上から溶きパテを塗って細かな凹みを埋めていく。こういう作業を幾度となく繰り返すのだ。その為、エアブラシではなく筆できっちりと色を分けて塗る方が効率的だった。
カウラ、仕上げるのはなんとも大変だったが、同時にしみじみと幸せも感じた。30cmオーバーで超獣と向かい合える事実、こんな日が来ようとはひと昔前までは考えられなかった。果敢なチャレンジを続ける杉本さんに対して細やかなエールとなるよう、これからも精一杯キット作りに励んでいきたい。
| 全高 |
パーツ数 |
付属品 |
材質 |
| 320mm |
23点 |
なし |
ウレタン樹脂 |
| 原型師 |
|
|
|
| 杉本 浩二 |
|
|
|
|